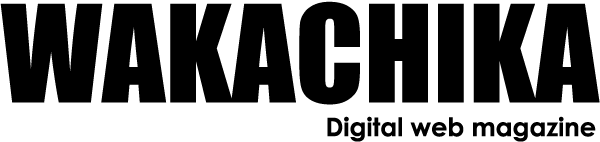2025年度は神戸青年会議所の委員長にもフォーカスし、各委員会での取り組みや想いを伝えます。また本年度のスローガン「Captivate ~世界に誇れる神戸へ~」にもとづき対談を通して「人の心を惹きつける」要素とは何かを考えます。
今回は、六甲の森と街をつなぐ活動を長年続けてこられたSHARE WOODS. 代表 山崎 正夫様をお迎えします。六甲材(六甲山の材木)を活用した家具や什器づくりをはじめ、教育現場や地域イベントとの連携を通じて「森と人」「街と人」を結び直す取り組みを展開されています。
本対談では、神戸のまちづくりや観光・教育・イベント運営に携わる委員長4名とともに、地域の資源をどのように活かし、誇れるまちとはどうあるべきかを考えます。

Special Guests
山崎 正夫(やまざき まさお)
SHARE WOODS. 代表。ドイツの木材メーカー勤務を経て独立。神戸市の六甲山をはじめとする里山資源を活用し、木材コーディネートを中心に活動。伐採・製材から流通、家具や什器の製作、市民参加型ワークショップまで、森と街をつなぐ取り組みを一貫して手掛けている。特に「カホンプロジェクト」では、木を使うことの意義を市民と共有し、単なる楽器製作ではなく「森を知る入り口」として全国的な注目を集めている。
SHARE WOODS. 代表 山崎 正夫(以下:山崎)
マーケティング戦略委員会 委員長 河合 孝治(以下:河合)
地域経済活性特別委員会 委員長 門野 裕太(以下:門野)
オータムフェスティバル特別委員会 委員長 酒井 将利(以下:酒井)
例会委員会 委員長 北岡 健太郎(以下:北岡)
総務委員会 委員長 和田 昴樹(以下:和田)
気づかなかった身近さに価値がある
和田:私は鈴蘭台に住んでおり、10分ほどで六甲山に行ける環境にあります。休日には散歩やハイキングにも行きますが、“六甲山の木がどう使われているのか”を考えたことはありませんでした。六甲材の取り組みを知って、とても身近に感じました。これまでの活動で、一番大変だったことは何でしょうか。
山崎:私は「やりたいことをやっている」という感覚が強いので苦労とは思っていません。
ただ振り返ると、独立してから最初の3年間はきつかったです。山で木を伐り、製材所で板にして倉庫に積むところまではできる。でもその先が見えない。
どう売ればいいのか、誰が必要としているのかもわからず、倉庫には材が積まれるばかり。夜中に倉庫を見に行き“不安で眠れなくなる”こともありました。
和田:想像しただけで胸が苦しくなります。その状況をどうやって乗り越えられたのでしょうか。
山崎:支えになったのは神戸の人たちの“地域愛”でした。「六甲の木を使いたい」「地域の資源を活かしたい」と言ってくださる方がいたのです。
2017年、市役所1号館のロビーに六甲材のベンチを設置したとき、市民の「六甲の木が市役所にある!」という反応は大きく、そこから家具や什器の依頼も入りました。ある女性が「いつも見ている六甲山の木が市役所で使われるなんて誇らしい」と声をかけてくださり、涙が出るほどうれしかったこともありました。
和田:木がただの資源ではなく、人の生活や思い出と結びつくことで価値が生まれるのですね。
山崎:その通りです。私が目指すのは“産業の復活”ではなく“関係性の再生”です。
森と街、人と人との関係をつなぎ直すこと。そのためには木をただ加工して売るのではなく、どう見せ、どう体験してもらうかが大切だと考えています。
最初は「伐れば売れる」と思っていましたが、外国産材には価格でも規格でも勝てない。
だからこそ“競争するのではなく、意味を共有すること”。
六甲の木だからこそ価値があり、神戸の人が日々見ている山の木だからこそ意味がある――その物語を共に体験してもらうことが突破口になると気づきました。

体験を共有し、学びを未来へ
北岡:私は毎月の例会を通して、会員に学びの機会を提供する役割を担っています。例会は単なるイベントではなく、会員にとって刺激や成長の場でなければならないと考えています。
山崎様は“森と街をつなぐ活動”を長年されていて、教育や学生との連携も多いと伺いました。森のワークショップや活動に学生が参加したとき、どんな変化や気づきが生まれていると感じますか。
山崎:学生や子どもたちとの関わりは私にとっても大切な部分です。
たとえば高校生が六甲山に入って草刈りや間伐を手伝ってくれることがあります。最初は「山に行ったらバーベキューかな」「焚き火で焼き芋かな」と楽しみ半分で来るのですが、実際は草刈りや枝打ちといった地道で大変な作業。想像と違って驚く学生がほとんどです。
でも一日やってみると「こんなに大変なんだ」「木を一本切るのにも技術がいるんだ」と実感が湧きます。
そして作業後に森が明るくなったのを目にすると「自分の手で森を変えられた」と達成感を持つ。
その体験が地域や環境に対する視点を変えるのです。だから森の活動は教育の現場としても大きな意味があると感じますね。
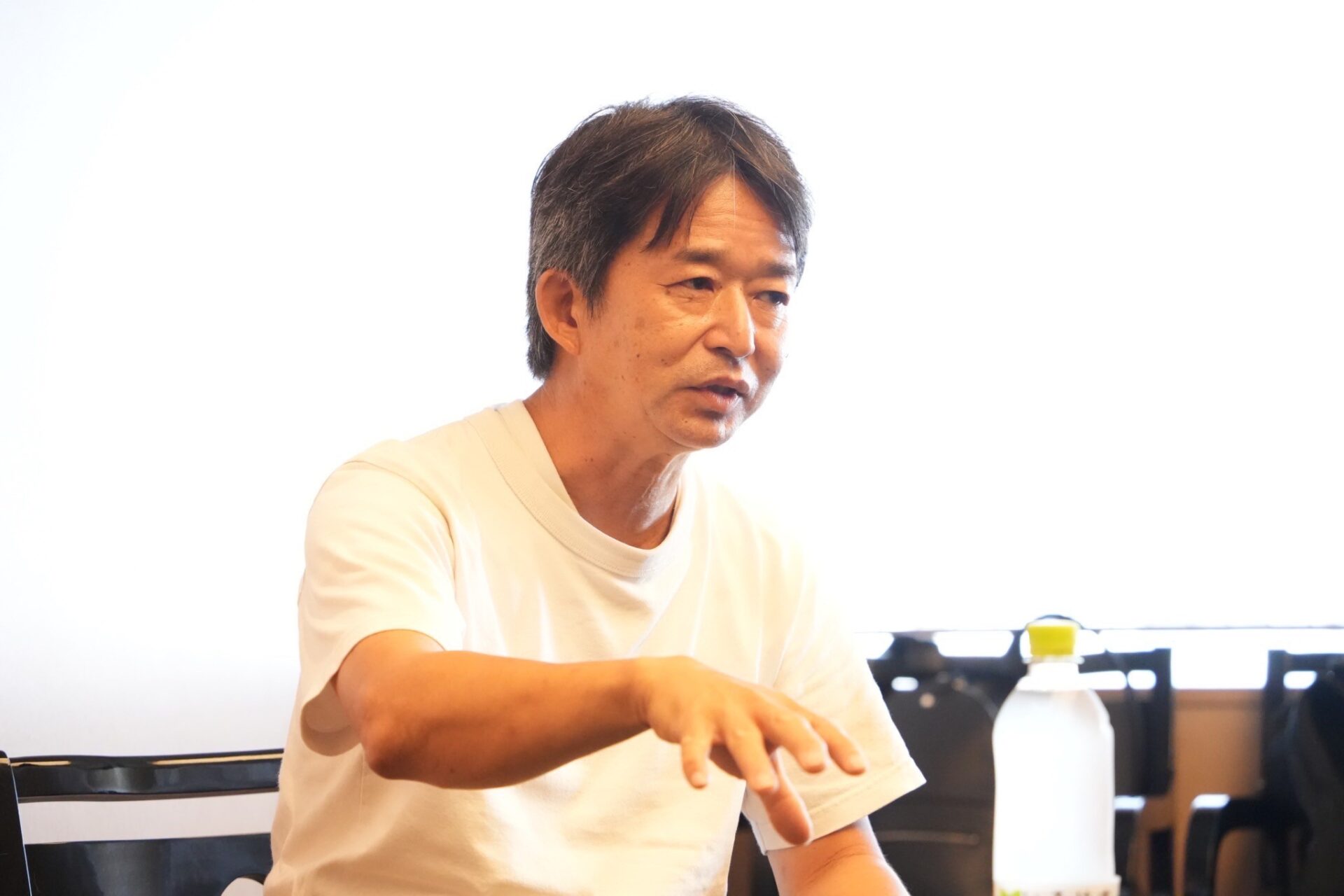
北岡:体験を通じて気づきを得ることはとても多いと感じています。
そのうえで、私たちの委員会が課題としていることが“主体性をどう引き出すか”という点です。全員が同じ温度で積極的に関わってくれるわけではなく、どうしても温度差が出てしまいます。
山崎様は学生や市民を巻き込んだ活動の中で、そうした点にどのように向き合ってこられましたか。
山崎:これは私もずっと悩んできたテーマです。
正直に言うと“全員を同じ温度で巻き込むのは不可能”だと思っています。
学生のプロジェクトでも最初は全員やる気満々でも、途中で離脱する子は出てきます。そこで大事なのは“無理に引っ張らないこと”だと思います。
むしろ、それぞれの興味や得意なことを見つけて任せるほうがうまくいくと思います。
クラフトが好きな子には木工を、発信が得意な子にはSNSをお願いする。役割を分けることで自然と主体性が芽生えます。
組織でも同じで“全員が同じことをやらなくていい”という柔軟さを持つことが、結果的に参加の幅を広げ、組織を強くしていくのだと思います。

観光は“地域の誇り”から生まれる
門野:私は“神戸の観光や地域経済をどう活性化させるか”という視点で事業を構築しています。
六甲材を活用した山崎様の取り組みは、まさに私たちのテーマとも重なる点が多くあると感じております。
観光や地域経済に直接的に寄与したと感じるエピソードがあれば教えてください。
山崎:観光といえば建物やイベントをイメージしがちですが、木材を使うことも立派な観光資源になると思います。
たとえば神戸阪急の店舗什器を六甲材でつくらせてもらったとき、「地域の木を使っているんですね」とお客様に声をかけられました。
その一言がきっかけで“神戸らしさ”を再認識してくださる方が多くいました。買い物を通じて六甲の森を意識してもらえる。
これは観光に近い体験だと思います。
また、市外や県外の人に「このベンチは六甲の木でできています」と説明すれば、それ自体が街全体を案内する“語り部”になります。
門野:観光資源は名所や名物だけではなく、日常の中に“神戸らしさ”を感じられる仕掛けが大切ですね。
一方で、私たち青年会議所の委員会はどうしても単年度で区切られるので、「成果をどう残すか」が課題になります。
山崎様のような取り組みを“次の世代に残す”ために意識されていることはありますか。
山崎:とても大事なご指摘です。
森の活動もすぐに成果が出るものではありません。木を植えても育つのに何十年もかかりますし、木を伐ってから流通に乗るまでにも時間がかかる。
だから短期決戦型の取り組みだけでは続きません。ただ1年の活動が無駄になるわけではなく、重要なのは“仕組みを作って残すこと”です。
例えば神戸市と一緒に立ち上げた「森の木プロジェクト」では、担当者が変わっても続けられるよう、外部団体と連携して仕組みを残しました。
人が変わっても事業が続く形にすることが大切です。
青年会議所も同じで、イベント自体が残らなくても、運営ノウハウや地域団体とのパイプを“資産”として残すことで、単年度の取り組みを未来につなげることができると思います。

当事者意識が街を動かす
酒井:私は今年で4回目を迎える「KOBE AUTUMN FESTIVAL」という神戸青年会議所が主催するイベントを企画運営し、食・音楽・アートなど神戸の魅力を発信する事業構築をしています。
そのうえで“どう街を巻き込み、どう神戸らしさを表現するか”を常に考えます。
山崎様は森と街をつなぐ活動をされていますが、地域を巻き込みながら“地域らしさ”を伝える工夫にはどんなものがあるでしょうか。
山崎:街のイベントと森の活動は違うようで共通しています。
大切なのは“外から人を呼ぶ前に、まず地域の人に当事者として関わってもらうこと。
森の活動も最初は冷ややかな目で見られましたが、地域の人が「自分たちの資源を使っている」と実感してから応援の輪が広がりました。
イベントも同じで、ステージやワークショップに地域の子どもや団体が参加してもらうことや、商店街と連携して出店してもらうことで“自分たちの祭りだ”と感じてもらえるようになります。
酒井:地域の人が“自分ごと”にしないと一過性で終わってしまうのですね。
大規模イベントになると、派手さや数字に引っ張られ地域が置き去りになることもがあるかと考えますが、規模と地域密着のバランスについてどう考えますか。
山崎:私が大切にしているのは“地域の満足度”です。
例えばカホンのワークショップも、最初から大規模に広げようとはせず、一人ひとりに丁寧に森の話をして「気づき」を持ち帰ってもらうことを重視しました。
その積み重ねが広がりにつながる。イベントも同じで、まずは地域の人が「楽しかった」「また来たい」と思える質を大事にすること。
集客はその後で十分です。たとえ来場者数が減っても、地域の人が誇りを持てるなら、それが本当の成功だと思います。

結びに
河合:山崎様との対談を通して、地域の資源や活動には私たちが日々の暮らしの中では気づかない価値が隠されていることを学びました。
体験を通じてこそ見える学びや、役割を活かし合うことで広がる主体性。観光や経済の活性化においては、特別な名所や名物だけでなく、日常の中にある誇りが原点となること。
そして、イベントを成功に導くのは規模や数字だけではなく、地域の人が当事者として関わり、満足と誇りを感じられる場をつくることが大切だと確認することができました。
これらの気づきは、地域に根ざした活動を展開していくうえでとても大切なことだと感じております。
明るい豊かな社会を実現するために取り組む我々神戸青年会議所にとって、とても貴重な機会となりました。
本日の対談を活かして今後の事業を展開してまいります。