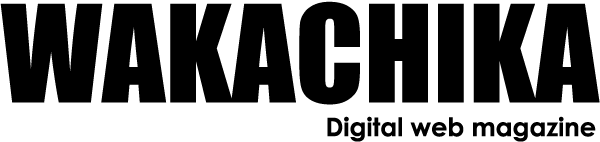上根理事長:私たち神戸青年会議所は、明るい豊かな社会の実現をめざして神戸市内をより良くする活動を展開している青年経済人団体です。単年度で役職が交替する組織体制になっています。本年度は、スローガンを「Captivate ~世界に誇れる神戸へ~」と掲げており、この言葉には「人の心を惹きつけるまちへ、人へ」という願いを込めています。
このたび、9月1日にイギリス・ロンドンの名門校『North London Collegiate School Kobe(NLCS Kobe)』が神戸市東灘区の六甲アイランド『Asia One Center』に開校されたということで、神戸にこのような教育機関ができたことをとても嬉しく思います。 国際性や多様性を重視しながら、日本ならではの文化や価値観も教育に反映させる “世界水準の学びを提供する場”の魅力や、池田様ご自身の教育方針、ライフワークについてもお話を伺っていきたいと思います。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
池田 代表取締役社長(以下:池田)
上根 理事長(以下:上根)
Profile

池田 浩八(いけだ こうはち)
八光エルアール株式会社 代表取締役社長。
大阪府堺市出身。英国アストンマーティンやランドローバーなど、世界的な高級車ブランドの正規ディーラーとして事業を展開し、「COLOR OUR LIFE ― 人生に彩りを」という企業理念を掲げる。単なる車の販売にとどまらず、憧れの一台を通じて顧客の人生を豊かに彩る体験や、車を介したコミュニティーの創出に力を注いできた。同グループが運営する六甲山サイレンスリゾートにて神戸の夜景を背景にしたオペラナイトなど、車を超えた文化的な取り組みにも積極的に関わる。また、海外でのビジネス経験から日本の教育課題に強い危機感を抱き、次世代がグローバルに活躍できる環境を整えるため、トップレベルのインターナショナルスクール「NLCS Kobe」の誘致に尽力。六甲山の自然や神戸という地域資源を生かし、国際都市としての発展を見据えた新しい挑戦を続けている。
1 NLCS Kobe設立の想いについて
上根:まずは池田様の企業理念をお聞かせください。
池田:企業理念は「COLOR OUR LIFE」、人生に彩りを届けることを大切にしています。僕たち(八光エルアール株式会社)が販売しているのは、ただの車ではありません。
車は移動の道具ではなく、乗ることで気分が高揚し、人生の一瞬を彩る存在だと思っています。
だから僕たちは「夢を販売している」「豊かな時間を販売している」と表現しています。「いつか成功して、憧れのアストンマーティンに乗りたい」といったような人々の夢に寄り添うように。
車という共通点から人と人がつながり、経験や出会いが広がっていく。
そんな豊かな時間を提供するのが、僕たちの目指す姿です。
上根:人生に彩りを届け、販売しているそのものではなく、共に過ごす時間や夢を売るという考え方にとても共感します。
そんなカーディーラーでもある御社が今回新たに教育分野に挑戦されることとなったきっかけや経緯はありますか。
池田:僕たちがもう一つ大切にしているのが教育です。
車を通じて出会ったファミリーにとって「次の世代の未来をどう彩るか」は大きなテーマでした。
僕自身ヨーロッパやアメリカとビジネスを通じて関わる中で、日本人が世界の舞台で相手にされにくい現実を痛感しました。
海外のオーナー同士が「学校の旧友」としてつながる中、日本人は誰もその輪に入れない。
このままでは日本が取り残されると危機感を覚えました。
だからこそ、次の世代が世界のゲームボードで活躍できるように、神戸にトップレベルのインターナショナルスクールをつくることを決意しました。
上根:『North London Collegiate School』(以降NLCSと略)はイギリス国内でもトップクラスの評価を得ていて、卒業⽣の40%が世界トップ20の⼤学へ進学を果たしているそうですね。インターナショナルスクールの中でも、この学校を誘致されたポイントは何だったのでしょうか。
池田:まず大切にしたのは「コミュニティー」です。世界のトップ校のコミュニティーは規模も質も違います。アメリカ人やイギリス人だけでなく、本当に多国籍の人々が集まり、学生時代の友人関係が将来の国際的なビジネスのプラットフォームになります。国を越えた人脈が自然と築かれる、そんな環境を提供できる学校であることが重要だと考えました。
さらにNLCSを調べると、教育実績が群を抜いていました。国際バカロレア(IB)の平均スコアが45点満点中43点と、イギリス国内1位、世界でも3位という水準です。卒業生の約40%が世界のトップ大学に進学しており、日本には存在しないレベルの成果を出しています。アカデミックな面で間違いなく世界トップクラスだと確信しました。
もう一つ大きな魅力は教育理念です。NLCSは詰め込みではなく「学ぶことは楽しい」「子どもがハッピーであることが最も大切」と掲げています。子どもが興味を持った瞬間を全力で後押しし、学びに上限(ルーフ)を設けず、基盤(ベースメント)を作ってどこまでも伸ばすという考え方です。その教育観があるからこそ世界トップの実績につながっているのだと感じました。ちょうど日本進出のパートナーを探していたこともあり、強く惹かれたのです。
上根:探求型教育を基本としながら、子どもの個性を磨くカリキュラムも多数用意されているようですね。海外からも評価される、まさに「世界に誇れる教育」ですね!

2 六甲山の活用について
上根:世界最高レベルの学校が神戸に開校することは本当に喜ばしく、日本の教育だけでは飽き足りないと感じられる親世代の方々にも歓迎されるニュースであると思います。
今回のNLCSの誘致が神戸の未来にもたらす影響に期待は高まるばかりですが、あえて大阪ではなく神戸(兵庫)に誘致しようと思われたのはなぜですか。
池田:理由のひとつは「六甲山」という環境です。コロナ禍を経て、都会での生活は便利な一方、人間の機能が退化する等、大人も子どもも強いストレスにさらされていることが分かってきました。「都会にいる必要はない」と気づき、むしろ山の自然の中で暮らし、学び、働くことの方が人間らしく、可能性を最大限に引き出せるのではと考えました。
実際にイギリスの関係者が視察に来られ、予定地を見て「ここは360度の絶景が広がり、世界一の学校になる」「世界中から人が集まる場所になる」と高く評価され、居住者ではない彼らから改めて神戸や六甲山の素晴らしさを教えられたのです。
上根:六甲山の気候は温暖少雨の瀬戸内気候というのも特徴の一つですね。
明治維新開港のあとで、外国人たちがこぞって山上に別荘を立て、日本最初のゴルフ場も開設され、1930年頃には高級リゾート地としても見られ、憧れの場所として人気を集めた保養所も多い場所であったにもかかわらず、バブル崩壊によりそれらは次々と閉鎖されてしまい、山上は寂れる一方でしたが、近年は少しずつその魅力に注目する外国人観光客の方も多いですね。
池田:六甲山という環境は関西のなかでは唯一無二のものなので、そこはポイントになると考えています。
今、六甲山の山上開発について調べているのですが、海外の投資家の方々がとても興味を持たれています。軽井沢は時価がどんどん上がっていて、都心部まで1時間で行くことができますが、六甲山は都心部までもっと近いことも注目を集めているポイントだと思います。
しかも空港も国際化していますし、シンガポール・香港の方たちは色んな国に資産を持ちたいという方が多く、東京は時価が上がっているので、関西をターゲットとして検討している方は多いです。
上根:世界中を探しても、こんなに美しい自然がある山頂付近で、生活に関連する銀行や学校があり、車で15分走れば、病院やスーパーがある市街地にも行けるという距離感が六甲山の魅力であり、神戸市も六甲山を活用するスマートシティ構想を立てていますよね。
御社が2019年に開設された「六甲サイレンスリゾート」のカフェもインバウンドの方が増えてきているそうですね。観光と言う分野でいえば、神戸は通過型都市で経済が回りにくいといった点も課題の一つです。
池田:奈良にJWマリオット・ホテルがオープンして以来、インバウンドが多く宿泊するようになったと思いますが、全くその発想だと思っています。神戸でも外資系のホテル誘致など、国際都市としてよりポジティブになればと思います。
上根:仰る通りですね。インバウンドの方が旅行する際に参考にされる指標の一つとして、外資系ホテルの所在というのは一つのポイントになると感じます。神戸は京都 大阪 瀬戸内とどこへ行くにもとても便利な場所なので、神戸を起点に各地へ遊びに行くという滞在型観光を推進していきたいところです。
池田:近くIR関係のマネージャーレベルの方々が約4,000人近く日本に来られるそうです。
その滞在先として六甲アイランドも候補になりますが、彼らにとってはプレミアムなインターナショナルスクールがなければ移住先として選ばれません。
最近では大阪府・大阪市が財政特区に選ばれ、北海道・東京・福岡と並んで、海外の金融家や投資家に対して税制面などさまざまなメリットを提示しながら誘致を進めています。
その取り組みの一つに、プレミアムインターナショナルスクールの誘致も含まれています。こうした動きを背景に、関西には今後さらに外国人が増えていくと考えられます。そのタイミングで外資系ホテルが整備されれば、まちの流れが大きく変わるはずです。
1クラスが最大22名、1学年につき2クラスですので、1学年最大44名。子供8名に対して1名の教員及びスタッフがつくことがNLCSの基準で、それに倣っています。これにより、それぞれの子どもたちに合わせた個別教育が進められます。日本独自のプログラムにもこだわりをもっており、例えば“剣道“など日本ならではの“道”とつく分野はできる限り数多く実施したいと考えています。
その中から子ども達の興味をもつものを見つけ、課外活動を採用したいと考えています。
上根:子どもたちの意欲をかき立てながら、日本の文化を重んじたプログラムが展開されるのは良いですね。
日本には素晴らしい文化が沢山あるにもかかわらず、継承やそれを海外の方へ魅力的に語るといったことには課題があるように感じています。
世界を舞台にするためには日本人であることを誇りに思い、発信できるようになる必要があると思います。

3 世界を舞台に活躍できる人財育成について
上根:教育という所で少し掘り下げてお話していきたいのですが、今現在日本が抱える教育環境の課題、もしくは日本に不足している教育環境については、どのような考えをお持ちですか。
池田:日本の教育を否定するつもりはありませんが、学習要綱が11年ごとにしか見直されないのは時代の変化に追いつけていないと感じます。
例えばIBはAIやロボットの進化に合わせて「これから必要なソフトスキルTOP10」を毎年発表し、それに基づいてカリキュラムを更新しています。アップデートの速度が全く違っており、日本ももっと柔軟に変化していく必要があると思います。
海外の人から「当然やっているでしょ」と問われる内容でも、日本は対応できていないことが多い。これが、日本人が世界で認められにくい要因の一つになっていると感じます。
日本の伝統文化を現代に活かし、世界で発信していくことはとても大切で、そういった日本人のアイデンティティを養うことが教育の大事な柱です。
上根:日本人のアイデンティティを養う教育を重んじるという点にとても共感します。
神戸青年会議所では、本年度大学生と共にまちの社会課題を解決し、未来を構想しようというテーマの下でプログラムを展開しています。
在神企業や各分野の専門家、そして行政などさまざまな視点から彼らの考える課題解決策を共にブラッシュアップし、実現性などを検証して最後は神戸市へ提言するといったようなものです。
NLCSでも企業と学生が関わる機会創出などは考えられていますか。
池田:関西の企業と学生を早い段階から関わらせたいと考えています。
将来トップ大学に進むような子ども達と企業が接点を持てば、新しい開発やコラボが生まれる可能性がある。
彼らが大きく成長した時には、全員に株式会社をプレゼントしたい。そうすることで「神戸の学校に出資したい」と考える人材が生まれるはずです。
日本にはまだない、企業と学生が繋がることができるプラットフォームを神戸から築きたいと思っています。
上根:とても心強いお考えです!神戸は転出する若年世代が多いことなどが影響して人口減少が続いており、現在神戸市の人口は150万人を割っています。
若年層の他都市流入を防ぎ、再び国際都市としての存在感を出していくことができればと思います。
ウォーターフロントも徐々に整備されており、今後益々活性化していくことが期待されます。今は神戸市の人口も150万人割っています。
池田:今後神戸は、インターナショナル神戸になっていくと思います。この前、韓国の某トップIT企業の経営者と会食した際に、神戸に自分たちが拠点を構えてスタートアップ向けに自分たちのプラットフォームを築きたいという想いを聞いていますし、シンガポールとかの企業もそういうお話も聞いていますし、そのような企業が神戸に入ってくることですごく変わると考えています。

4 最後に
上根:先日ホームページで池田さんと東京大学教授 慶應義塾大学特任教授の鈴木 寛さんとのトークセッションレポートを拝読させていただきました。
その際にもテーマに挙がっていましたが、教育環境の未来を考える時 「ウェルビーイング」は一つのカギになるかと思います。
最後に、日本におけるウェルビーイングの定義とは何か、ご見解をお聞かせください。
池田:教育環境におけるウェルビーイングは外部的な環境と内部的な環境の両方があると考えています。
外部的な環境は六甲山のような環境で過ごすことで、色々なストレスが緩和されるという所が六甲という環境の良さの大きい所だと考えています。
スコア・評価・ランキングっていうのが子どもにとってすごい重圧になっています。
教育先進国であるシンガポールでは小学校2年生までテストを禁止しました。
小学生2年生までの時期・年齢で感受性が豊な時期に評価されると親や周りからのプレッシャーをかけることは良くないことが分かり、禁止にされたそうです。
教育がウェルビーイングを低下させることがあってはいけないと思いますし、学ぶことが楽しいって大人になって分かることが現状だと思います。
だから将来僕らの学校は大人にも学びをいつか開放したいと考えています。
学びはウェルビーイングを高めるコンテンツだと考えています。学習欲というものは人間のウェルビーイングとリンクしていると思います。